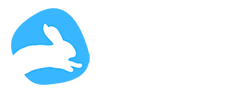練習後もお名前(女)から一向に連絡はなかった。
結人も姿はみてないらしく、3人の中で実質会ったのは英士だけとなる。
その英士も、昨日と同じ態度のままで、多くは語ろうとはしなかった。
携帯電話の着信音が部屋に鳴り響いて、画面には“友人の名字 友人のお名前”の文字に、少し肩を落とした。
もしお名前(女)からだったなら――随分と救われたかもしれない。
「もしもし」
『…………』
電話に出たが友人のお名前は喋る様子はなかった。
(まさか変な事件に巻き込まれて電話だけかけてきた、とかじゃないだろうな?)
物音一つしない雰囲気が不気味だった。
「友人の名字?」
『……に言った?』
「え?」
「お名前(女)に何言ったって聞いてんのよ!!」
叫ぶ声はどこか悲しげで、ムードを壊すように鼻水を啜る音が響いた。
「偽名?」
「お名前(女)泣いてた。電話にも出ないから家に行ったら泣いてたから……。理由、聞いても答えないし……だから真田が何か言ったと思ったの!』
練習を見に来てもらう約束を取り付け、その約束どおり出掛けていたなら、疑うのは当然だろう。
そこで、自分に会っていないとしても。
「俺、今日偽名に逢ってない……」
『へ?』
友人のお名前は間抜けな声を返す。
「俺は逢ってないけど英士なら会ったって。結人から、英士が帰ったって言ってたって、練習後に聞いた」
『じゃあ、郭君に聞けばいいのね? 真田、電話番号教えなさいよ』
「まぁ、落ち着けよ偽名。 英士には俺から話すから」
『本当に?』
「本当だって!」
『わかった。理由を聞いたら直に私に電話する事』
一馬は急いでアドレス帳から英士を見つけて発信ボタンを押した。
一馬が自分が話す、と言った理由は、実は別にある。
ファーストフードの後から、機嫌がどことなく悪かった気がする。
その時は混乱して気を回してなかったが、思い返してみれば――。
数回呼び出し音が鳴ると、いつもと何もかわらない英士の声が聞こえた。
『もしもし……一馬?』
「英士!……急に電話して悪い」
(気のせい、か?)
普段通りの反応に、気分が晴れていく。
きっと思い過ごしだったんだ、と一馬は話を安心した。
『別にいいけど……どうかしたの?』
「名字のことだけど、今日会ったんだよな?」
“名字”という単語を出すと英士が急に黙ったが、一馬は黙った理由を気にも留めない。
「泣いてたって、友人のお名前から電話があって……。英士なら何か知ってるかと思ってさ」
一馬が言い終わっても英士は黙ったままだ。
「英士?」
『一馬……名字さんを泣かせたの、俺だよ』
最初は何を言われたかさっぱり解らなかった。
高熱で思考回路がはっきりしないように、その言葉が脳内でぐるぐる回る。
「え?」
『言ったんだ名字さんに。“一馬に近づくな”って。そうしたら、帰っちゃったんだ』
「平然と言うなよ! 英士が前から名字の事、良く思ってたのはわかってたけどさ!」
状況が整理できず、言葉に詰まって何も言えなかった。
『悪かったとは思うよ、でも一馬の悲しむ顔は見たくない。それに彼女は一馬の事……』
「英士、俺、英士や結人の事……大切な親友だと思ってる。でも名字もそれぐらい大切なんだよ……!」
耳鳴りがしたと思った途端、電話が切れる。
「英士!?……ああ、もう!!」
携帯電話を握る手が熱くなる。
一馬は急いでお名前(女)の家に向かった。
「なんで俺がこんなことしてるんだろう……」
電話を切ったことも、彼女に傷つくことを言ったことも、全く自分らしくない。
自分が自分じゃないようだ。
一馬と電話を切ってから、数秒も経たずに電子音が鳴り響く。
英士は迷うことなく、通話ボタンを押す。
「もしもし」
『郭君ですか? あの、名字です。名字 お名前(女)です』
「あ……」
電話が鳴った時、画面をちゃんと確認せずに出てから驚いた。
あのタイミングで電話がくるならば、一馬だと思ったが、一馬はあれだけ言われて冷静になれないほど子供じゃない。
『郭君に……どうしても言わなきゃいけない事あるから電話したんだけど、良い?』
「良いよ」
英士に断る理由はなかったし、また何か言ったなら論破してしまえばいい。
『今日、練習に行った時に言われた事なんだけど……その通りなの。……信じられないのって自分でも悲しい事だって思うから。だから私、郭君に感謝してる。私、郭君の事信じる!若菜君も信じる。もっと人の事、好きになりたい。一馬君ともっと仲良くなりたい、だから……』
言葉が紡がれている間は、まさに一瞬だった。
早口ではなかったが、決して言葉を挟ませなかった。
まるで、言葉を知らないこともが、親に伝えたいことを必死になっているようだった。
その光景を想像すると、笑えてきた。
「ははっ……名字さんらしいというか」
『は、はは、何言ってるかわかんなくなってきちゃった』
「俺は、てっきり文句でも言うかと思ったよ」
『文句?! 私、郭君にそんな事言う度胸ないよ」
「俺もキツイ事言って悪かったね。ごめん」
『郭君、あの……また皆で夕飯食べに来てね。本当、ちょっとだけど……私、変わってると思うから』
電話口の彼女はきっと必死で笑っているのかもしれないけど、かすれた声を聞くとちょっとだけ、胸がチクリと痛んだ。
「ありがとう。ところで、一馬の事どう思ってるの?」
『真田君のこと? 優しいし、気使ってくれるし……とってもいい人と思う』
「それだけ?」
『それだけ――もっと仲良くなりたい。ずっと一緒に居たい』
「“ずっと一緒に居たい”ね。それ……一馬に言ってみたら?」
『かなり恥ずかしくないですか?!』
「……一馬から電話ないから、きっと名字さん家に行ったんじゃない?」
『うち?!』
それと同時に受話器の玄関の方から呼び鈴が鳴る。
『え?!』
「きっと、一馬だよ」
『ありがとう、郭君』
「こちらこそ」
長く話していたつもりはなかったが、一馬が急いで向かっても10分は掛かる距離だ。
話し出したら、言葉が自然に出てきた。
なじることから、励ますこと、全部。
(一馬が好きになっただけの事は……あるか)
この感情をなんと呼ぶか知っている。
「失恋、か」
椅子の背もたれに、深く寄りかかって、携帯電話の番号をアドレス帳に登録する。
登録したのは一種のけじめだった。
(もしこのまま友達にならなかったら、違ってたのかな……)
お名前(女)は急いで玄関に行くとドアを開ける。
「真田君!」
「名字!」
お互いに何を喋るべきか解らず、ただ黙り続ける沈黙に耐え切れず、お名前(女)が
「真田君……上がってよ。お菓子とかあんまり無いけど」
「あ、うん」
玄関を通って居間につくと、全て灯りは消えていた。
まだ夜の7時を回ったばかりで、寝るに早すぎる。
ごみ箱には、ティッシュの塊が詰め込んであり
(泣いてたんだな……)
一馬を切なくさせた。
「ちょっと座ってて? 飲み物、持ってくるから」
お名前(女)は台所に行くと、冷えた麦茶のグラスを持って帰ってくる。
「はい、どうぞ」
「ありがとう」
そっと口をつけると、冷たさ体にしみて、走ってきた一馬には丁度良かった。
「……私、真田君に言わなきゃいけない」
「ああ……」
「家に来たって事は真田君、郭君と話したって事だよね?」
「ある程度は……」
「私、もっと人を好きになりたい。人を信じたい。郭君に言われてようやく気付くとか馬鹿だよね。私と仲良くしてくれる?」
「当然!俺、名字の事、嫌いにならないって!」
「本当? ありがとう嬉しい」
これが一つ丸くなった笑顔というのか――笑顔がすごく眩しかった。
「俺! ……名字の事、好きなんだ」
「う、ん……ありがとう。あはは、先言われちゃったな……」
「名字?」
「真田君」
お名前(女)は俯きながら、右手を出して
「よろしくお願いします……」
とだけ呟く。
一馬が驚いたように手を握ると、お名前(女)もぎゅっと握り返した。