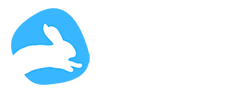ラクロアのことをトールギスと話をしてから数日経つ。
シュウトはこの生活に慣れつつある。
「……慣れてもこまるよね……」
そうだ、慣れてはいけないのだ。
自分はネオトピアに戻り、ダークアクシズを倒すという目的があるのだから。
何か情報をつかみ、帰れる手立てが無い以上、こうしているしかない。
急にネオトピアにいる、あの3人の声が心を過ぎる。
本当にどうしているのだろうか?
一瞬、もっと深くまで考えようとしたが、シュウトは別の話題へと切り替える。
数日経つが、この城から一歩も外へは出ていない。
城内でやることも、限られているし、それ以前に暇だ。
決まりだ。
シュウトはそっと部屋のドアから廊下へと出る。
地図もなく、何処へつながっているか等わかるはずもない。
以前、部屋から出て右に行くと階段があったのを覚えている。
なら、と思い、シュウトは部屋の扉の前から右へと歩き始める。
「あ!!」
階段と思しきものを見つけ、駆け足になる。
が、丁度、階段へと降りる曲がり角で誰かとばったり出会い頭になる。
「へ……?」
シュウトはついつい間抜けな声を出してしまう。
自分以外の人間が目の前にいるではないか。
金髪で紅い瞳が特徴的な人。
ラクロアの人間は石化しており、まさか生き残った人がいるとは・・・・。
「シュウトか……何故、ここにいる?」
あれ?
何故、自分の名前を知っている?
それに聞き覚えのあるこの声。
「え……トール、ギ、ス……?」
「オレがどうかしたのか?」
「だっ!……だって!!」
声と言葉遣い。
やっぱりトールギスだとしかいいようが無い。
「だって……トールギスは騎士ガンダムで……」
「――……そうか、こっちを見るのは初めてだったな」
一瞬、顔を曇らせたトールギスだが、驚いている理由がわかったのか、普通の表情に戻る。
「トールギスって人間だったの?!」
「いや、違う。この方が便利だから、魔法でこういう形をとっているにすぎん……」
「へぇ~……それって誰でも出来るの?」
「魔法を取得した、騎士ガンダムならばな。
シュウト、お前に使った魔法と同じ系統の魔法だ。秘術だから、知っているものは少ないだろうがな」
シュウトは珍しそうにまじまじとトールギスを見る。
そういえば、声や言葉遣いだけではなく、なんとなくだが雰囲気が同じだと気がつく。
トールギスを人に例えるとこんな感じなのかと、ついつい納得してしまう。
「トールギス様ー!」
階段の下から彼を呼ぶ声が聞こえる。
バタバタと忙しく、駆け上がってくる2つの足音。
「トールギス様、こんなところにいたんですか……」
丁度、170センチ程の背丈の男性が2人。
シュウトは、今度は驚かなかった。
もうトールギスで十分すぎる程、驚いたから。
魔法が使え、その魔法さえ知っていれば誰でもつかる。
ならその2人もそうなっても当然ではないか。
さすがはミラクルな魔法の国・ラクロア
「あ、トールギス様!シュウト君とお話中だったのかー……」
自分の名前を知っている。
トールギスから聞いたのか、それとも以前に一度、会っているのか。
この場合は後者だろう。
軽い口調で、赤い髪の毛をしたメリクリウスが言う。
「用件は、なんだ?」
「い、いえいえ~!先にシュウト君との方をどうぞ~!」
それを聞いて何事も無かったの用に、トールギスはシュウトと話を続ける。
「それより、何故、こんなところにいる?」
「え……あ~……お城の外、行って見たくて……」
「それは無理ですね、シュウト君」
突然、口を開いた青髪の男性。
「ヴァイエイトの言うとおり、それは無理だなー」
「なんで?」
「簡単なことだ。ラクロアにはダークネスマナが大量に存在している。
そのせいで、動物が凶暴化しているのだ……生身の、しかも人間のお前が外に出たらどうなるか想像はつくだろう?」
「なら、今度、俺が連れて行ってやるよー!」
その発言にトールギスは何も言わずにギロリと自分の部下をにらみつけた。
【生身の、しかも人間のお前が外に出たらどうなるか想像はつくだろう?】
警告された後は、言いつけを守り城内部にいるシュウト。
それでも退屈であることには変わりない。
外を見ていると、翼の騎士の姿が過ぎる。
それに加えて痛々しい思いになる。
きっと、自分の世界とこの世界の文字は違うので本も読めないだろう。
「はぁ……」
溜め息をついても何も変わることはなく。
部屋の窓から上半身のみ、垂れ下がって見ても、変わることない。
「あれ?」
垂れ下がっていた身体を勢いよく起こし、窓の下を見る。
城の壁の近くに生えているもの。
他の花は枯れているのに、数本だが、花やつぼみがついている。
それは、今までに何度も自分がよく見ていた花とあまりに似すぎていた。
ラクロアンローズ。
それでもその花は紫ではなく、赤色だった。
今の現状で、花が育った姿など、ありえるだろうか?
それだけ珍しい。
もちろんのこと、シュウトはもっと近くで見たいという気持ちが出てくる。
が、先日の警告のこともあり、すぐには行動へと移さなかった。
それでも見たい。
幸い、階段で1階へと降り、窓から外に出ても大丈夫なようだ。
その甘さが命取りだったのだ。
1階へと降りた後、窓から禁じられていずはずの外へと出る。
ラクロアンローズと思われる花はそれはそれは美しいものだった。
これが国中に咲いているのかと思うと、ゼロが自慢したくなるのもわかる気がした。
色違いの花があるかどうかは、わからない。
けれども、やはり「綺麗」という感情に変化はない。
こういう時には、普通1本ぐらい持ち帰るのだろうが、
こんな現状で咲いた花だからこそ、枝から折るという気持ちが引ける。
「うーん、どうしようかなぁ……」
考えている間に何故か背後に気配がするので、シュウトは何も考えずに振り返る。
「ごめん!勝手に出ちゃ……――うわぁ……」
両手を合わせて謝るポーズから、シュウトの表情は一気に歪む。
シュウトの表情は一気に歪む。
真後ろにいたのは、外に出てはならないといっていた原因がいた。
酷く凶暴そうな顔に牙と爪。
確かにこんなのに襲われたら一溜まりもないだろう。
だが、今自分はその襲われるという立場にいるのだ。
今更になって、シュウトは外に出たことを後悔し始めるのだった。
そして現在へ至る。
シュウトはチラリと外へと出た窓を見るが、距離は3メートルほど。
走って入ろうとした瞬間にきっと、と思うが想像したくはない。
人々が石化し、食のためにとっていた獲物の動物もきっと、石化したのだろう。
だから、このように騎士ガンダム・人間問わず、襲うようになった。
この状況から見て、結果を言えば、助からないだろう。
ネオトピアとは違い、発明品があるわけでもなく。
いざとなったら助けてくれれた彼らが居るわけでもない。
怖い。
そんな感情が心を染めた。
絶対絶命だとしか言いようがない。
自分にはまだやりたいこと。
やらなければならないことが残っているのに。
こういう時に限って、いい名案が思い浮かばない。
あの3人の名前を呼べば良いのに。
『なのに何故、この名前がでたのかな?』
「……トールギス!!」
叫んだ途端にシュウトはぎゅっと目を瞑り、その後に凶暴化した動物が地面を蹴る音が聞こえる。
来る!
そう、思った存在は何秒経っても来ない。
恐ろしい気持ちになりつつも、うっすりと瞳を開ける。
視覚の先に入ったのは、血を流して地面に倒れているあの凶暴化した動物。
冷静に考えてみれば、痛いと思う箇所はない。
うっすりと開けていた瞳をちゃんとパッチリ開ける。
凶暴化した動物に意識が行き過ぎていたせいか気がつかなかった。
倒れている動物の隣にいたのは紛れもなく名前を呼んだ彼。
トールギスだった。
今は人間の姿をしておらず、手に握られた剣には動物の血がべっとりと付いている。
剣を一回振り払うと、付いていた血が地面へと飛び散る。
それから、剣を地面に刺す。
「トールギス?」
「怪我は……怪我はないのか?」
彼は何事も無かった様にシュウトに問う。
「あ……うん、大丈夫……」
「そうか……」
その言葉を放った後に、シュウトはトールギスの方へと引き寄せられ抱きしめられる。
「もし、オレが通りかからなければどうなっていたか・……」
「あ、あの、ありがとう……それに、ごめんなさい……」
トールギスは何も答えない。
「無事で良かった」
本当に小さな声だったが、シュウトにははっきりと聞こえていた。
その一言だけで、シュウトの心はドキリとする。
それは 甘い囁き。