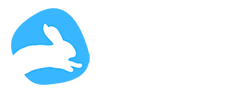1年中咲き誇る枝垂桜の上で杯を口付ける。
愛しいあの子がくるのが待ち遠しい。
人間のリクオがこの特別な空間へ訪れるのは夜だけだ。
つい数ヶ月前まではいくら名前を呼んでもうんともすんとも言わなかった。
祖父のぬらりひょんや組員も覚醒したことを喜ばしく思っているが1番は夜のリクオかもしれない。
襖が音を立てて開けば自然と唇が三日月形に変わる。
酒の味は別格ですぐに酔いが回る。
「リクオ、遅かったじゃないか」
「もう少しでテストだから勉強してたんだよ」
テスト、勉強……夜のリクオにとってはどうでもいいこと。
正しくは昼のリクオのことでどうでもいいことなんて1つもない。
1つの体に2つの意識があることは意外にも不便で、互いの意識をはっきり保っていられるのはこの空間だけ。
この空間で自分以外のことを考えられるのが癪だった。
杯に残るわずかな酒を一気に喉へ流し込むと枝から飛び降りる。
その時、そっとリクオの頭に手を置くのが夜のリクオは好きだった。
「またボクのこと子供扱いして!」
「そんなこたぁないよ」
どこからともなく取り出した煙管を吸ってからまた頭を撫でる。
頭一個分以上差がある身長は優越感に浸れる。
ほぼ主導権を握れることが嬉しい、昼のリクオは好ましく思っていないようだが。
「リクオがあまりにも可愛いからな。意地悪したくなっちまうのさ」
顎を掴んで無理矢理顔を向かせれば不機嫌そうな仏頂面でクスリと笑ってしまう。
「ほら、また笑って」
「そんなに子供扱いされるのが嫌なのかい?」
大きいため息をしながら昼のリクオは幹に寄りかかるように座り込んだ。
覆いかぶさるようにキスすると、昼のリクオは必死で着物を掴む。
またその仕草に興奮して息づきをさせないほど深くした。
煙管を吸った後のキスは独特な味がする。
酒の臭いも混じって、昼のリクオにとっては嗅ぎ慣れたものだ。
現実に互いに存在することはできなくても、この時間は本物だと、感じさせる一つの要素である。
「んっ!……ふ、んん……」
背中と腰を手で固定してしまえば、いくら体をよじったところで逃げることは叶わない。
苦しいのか顔を真っ赤にしながら背中を叩くと仕方なく唇を離す。
わざと舌を嫌らしくねっとり離すと唾液が残り、それをペロリと舐めて顔を離した。
「君って本当に嫌なことするね」
「気のせいじゃねぇか?」
「どうだか……」
呆れられているのに喉を鳴らして笑ってしまう。
笑い続ける夜のリクオに痺れを切らした昼のリクオは、着物の衿を掴んで
「おいっ――!」
触れるだけのキスをすると母屋に入って布団を被る。
だが、襖は開けられたまま。
さりげない気遣いが嬉しくて夜のリクオは煙管を吸った。