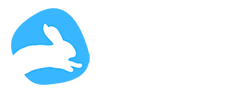電子音がして扉のロックが解除される。
ベッドの上に綺麗に整えられた着替えを置けば綱吉の仕事は終わりだ。
本当に何もない部屋の机にぽつりと置いてある瓶。
それを見たら苦い顔をするしかない。
ぎっしりと詰まっていた飴玉は数個入ってるだけで
(あんなに舐めてよく太らないよな)
なんて思ってしまった。
帰ろうと部屋を出ようとすると、急に扉が開いたので驚いて体を強張らせるが――相手も全く同じ状況なようで。
「綱吉、くん……?」
「おかえり、骸!洗濯物届けに来てたんだ」
「そうでしたか。ありがとうございます」
10年前に出会ったばかりの頃など挨拶どころではなかった。
自分との関係ではないけれど、こんな普通の関係を羨ましく感じる。
部屋に帰ってくるなり早々飴玉を手に取る骸を見てつい口に出す。
「骸、そんなに飴ばっか舐めてると太るぞ?」
からかいたくなって軽はずみで言ったのに、直ぐに言い返さない骸をみて「まずい」と思った瞬間――
「そうですね……太ってしまえばいいと思います」
胸元を刃物で抉られるような感覚に立ち眩みがした。
「本当の姿など変わってしまえばいいのです。綱吉君がいない今、この姿など必要ない」
唇が震えて、骸、と声が出なかった。
先程から続く胸の辺りを回る感覚が気持ち悪くて、この場に蹲ってしまいたかった。
「綱吉くんの唇は、飴のように甘いんです」
目と目が合って、頬に手を伸ばしてきたのが解ったが骸は触れることはない。
「……むく、ろ……」
背筋が鳥肌が立ち、やっと発せたのがこれ。
「僕もあまり気は長くないんです。手を出さないうちに帰りなさい」
骸の歯痒そうな表情に震える指先を見れば、綱吉は精一杯な気遣いだと解る。
早足で部屋から遠ざかれば急に身体から力が抜けた。
恐怖とも違う、涙さえも出なかった。
嗚呼、心はこんなにも虚無感で一杯だ。