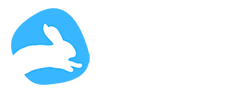快晴。
梅雨はあっという間に過ぎて太陽がアスファルトに照りつける。
そんな中、レイジは自転車で遅刻しそうな学校へ急いでいた。
「うおおおお!!」
レイジが自動販売機の前に差し掛かると――
「あ」
見慣れた姿があって、ふいに立ち止まってしまう。
「大空レイジ」
「氷室じゃん!って学校は?」
姿は私服で、学校に向かう気配はない。
「学校は行かない」
「そ、そっか」
会話は続くこともなく、プツリと途切れる。
「はぁ、俺もサボろっかな……」
レイジが呟いた時、既に隣りいた筈の氷室は居なかった。
辺りを見回すと数メートル先を歩いている。
「はや!!おい!ちょっ待てよ氷室!」
レイジも自転車に乗って氷室の後を追いかける。
氷室の隣りに来ると自転車を降りてレイジは言う。
「それより氷室!何、買ったんだよ?」
見ると、手には炭酸飲料が握られている。
「あ!それ飲みたかったやつ!……なぁ、氷室」
氷室は呼ばれたのに気がつきレイジの方を見たが、完全に先を読んでいた。
「それ、ちょっとだけくれ!」
飲めば間接キスになるが、そんなことも気づかず相手は手を合わせて頼んでくる。
缶の中には残り3分の1位。
「なぁ、頼むよ。あ!間接キスの気にしてんのか?」
それも一理ある。
そして氷室は一気に残りの炭酸飲料を飲む。
「あああぁあ!!」
レイジは叫び声を上げた次の瞬間、氷室はレイジを自分の方へ引きよせる。
唇が重なって、少しぬるい炭酸飲料が口に流れ込んでくる。
あまりに突然すぎて、レイジは自転車を離してしまい、耳障りな金属音が聞こえた。
「氷室、おおおお前!!」
「今度は奢ってやる」
氷室は空き缶をレイジの手に持たせた後、先に歩いていく。
「今のって――」
その場には顔を真っ赤にしたレイジ1人だけが残された。