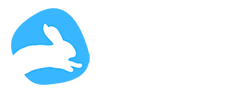(――あれからどれほどの月日が経っただろうか)
懐かしすぎる夢だった、とアヤナミは思う。
今から5年以上前の出来事だ。
あれから参謀部直属部隊の人数は増えた。
だが、ベグライターだったユキカゼは戦死。
身体を起こすと、久しぶりの気だるさについ苦笑いした。
「おっはよ~!」
朝から勢いよく、ブラックホークの執務室に入ってくるのは1人しか居ない。
「……煩い」
釘を刺しても、相手は落ち着く気配はない。
「アヤナミ様が言うんだから、少し静かにしてよね!」
「え~?クロユリは分かってないなぁ……煩いって言われると、もっとしたくなっちゃうんだよね☆」
「ヒュウガ、僕より子供なんじゃないの!?」
そういえば……、ヒュウガがフワリと何かをアヤナミの机の方に飛ばす。
「今来る途中で預かってきたアヤたん宛ての手紙」
クロユリを相手にしながら、不敵に微笑むヒュウガは相変わらず。
差出人は、直接政治に関与はしなくなったが未だに絶大の影響力を持つ元・元帥からだった。
今朝届いた手紙の内容を部下に話すと反応は疎らだった。
「えー☆」
「ええー!!?」
「……クロユリ様、落ち着いてください」
内容はザイフォントレーニングの一環として、週1で黒法術を見せて欲しいというもの。
参謀部直属部隊本来の顔は、黒法術師部隊だ。
それは国も認めており、軍という公の前で使えるのは自分の部隊だけになる。
「以前からお世話になっているミロク様の願いだ、断るわけにはいかない」
自分の部下は断るわけがない。
このアヤナミの顔に泥を塗る行為などする筈がないのだから。
申し出も早急過ぎたこともあり、その日はアヤナミ自身が出向くことで事は流れていった。
テイトには会っていなかったが、ここ数年も呼び出しがあれば変わらず屋敷には通っていた。
「ようこそアヤナミ君……急な申し出を受けてくれて助かったよ」
「いえ、私を指導者として招いて頂き光栄です……しかし、彼に黒法術を使わせるのですか?」
「……“覚醒”の兆しが見えてきてね、もう少し刺激を与えてもいいと思っただけさ」
この老人は相変わらず、手の内も見せない。
それがどれだけ今まで不快に思ったのか、計り知れない。
この部屋に辿り着くのに違ったのは、以前のメイドに会わなかったこと。
「テイトに話は通してある。優しく指導してやってくれ、きっと君もあの子を気に入るだろうからね……」
頭を下げれば、ミロクは来た道を戻って行った。
一応ノックをして、部屋に入ると5年前と何も変わりがなかった。
背丈は以前より落ち着いた少年がベットに上半身起こしたまま、アヤナミを見る。
「……こんばんは……」
「ミロク様から話は聞いているか?」
「黒法術を見せて頂ける、と……」
確かに間違った説明ではない。
逆に情報を与えすぎると、変な結果を招きかねないから得策だったかもしれない。
「基本的に、通常のザイフォンと大差はない。ただ大きければ大きいほど、術者は代価として命を捧げることになるが」
実際に黒く赤いザイフォンを作り出し、その状態を維持させるとテイトは身を乗り出してきた。
「……色が、ミカエルに似てる……」
そっと、両手がアヤナミのザイフォンに触れた。