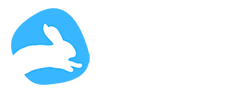「次はこちらの書類にサインをお願いします」
バルスブルグ帝国より北東に位置する要塞国家アントヴァルト侵略中も、アヤナミはデスクワークを欠かすことはない。
遠征中と言い訳せずに放棄すれば、その間も書類は溜まっていく。
まともにデスクワークをしない部下も居るならば、尚更だ。
テイトも配属当初より慣れた手付きで、書類を片付けて行く。
「へぇ~~~!」
やかましい声だと思い、主を確認したくて、書類から目を離す。
視界に入った人物を見て、瞬きを繰り返して動揺を抑えようとした。
(シュリ=オーク――――!!?)
「パパの船よりちっちゃいけど、なかなか良い船だな……気に入ったよ!」
向こうで他のブラックホークメンバーが固まっているが、テイトも同様に掛ける声を失う。
「本日付けでアヤナミ様のベクライターとなります、シュリ=オークと申します!」
アヤナミに敬礼する姿はまさしく軍人だが、声色が伴ってないのは気のせいではない。
「君、いつからベクライターに?」
首を傾げながらヒュウガが問うと
「だってパパがアヤナミ様のベグライターになりなさいって言ったんだもん!」
返答に、周囲は頭を抱え込んだ。
「それに、元・奴隷のテイト=クラインより、ボクの方がずっと名門家ですよ!」
それを聞いて、他のメンバーは凍り付き、テイトは無表情のまま、シュリを見つめていた。
* * *
シールドはあっけなく破られ、アヤナミの攻撃が地上へと放たれた。
(今のでどれぐらいの人間が死んだだろう……)
テイトの中に波紋のように広がった考えは、次の爆発音で掻き消される。
「各自持ち場に着け。……シュリとか言ったな、私のベクライターに相応しく、最前線で働いてもらおうか」
抵抗するシュリを無理矢理ヒュウガが地上へ放り捨てた。
その光景を見て、コナツとテイトは良い顔をしなかった。
「ヒュウガ少佐、僕も出ます!」
「オレも行きますね!」
シュリを追う形で2人は同時に戦艦から飛び降りる。
待機しているアヤナミの元へ戻りながら言う。
「あーらら……コナツもテイトくんも一緒に行っちゃった!」
ギロリと睨まれた瞳は、外の吹雪より冷たいやもしれない。
「……まぁ、あの2人が死ぬとは思えないけどね☆」
大砲を切られたのが、東部の地上戦合図となる。
真後ろで返り血を浴びたシュリが立ち尽くす中で
「目を逸らすな、これが戦だ!」
そう叫んだコナツは敵を蹴散らしていく。
テイトは掌から、即座にザイフォンを敵陣に放つ。
横目でコナツがこちらを確認したのを把握して、2人で上手く敵を分散させていく。
コナツの後ろには、使えない大きい荷物もあるおかげで、向こうをフォローしながら殲滅するのが無難だろう。
先にテイトばかり攻め立てれば、地形上あちらが不利になるのは明らかだった。
寒さで冷え切った身体など、気にならなかった。
東部が一掃し終わると、あの2人しか近くには居なかった。
本国から連れてきた兵が500という時点で、1人1人が倒すノルマは多い。
周囲を見れば敵陣ど真ん中に突っ込んでいった残りのメンバーも大丈夫だろう。
蹴っても動かない人間を見て呆然とするシュリの方が、ずっと自分より人間らしいと思う。
それに掛ける言葉を持つコナツも同様に眩しいとさえ、感じる。
違反すれば、食事は抜き、そして体罰が与えられ悲鳴を上げた。
そんなことを何度も繰り返していれば、あっという間に栄養失調に陥りますます動けなくなる。
犯すことが当然だった、しなければこちらが死ぬ。
ミカゲと過ごした日々を思い出せば心は嬉しさに満たされる。
あっという間に過ぎた日々に悲しみなどなくて。
「 」は、故郷と同様に、雪の中に埋もれてしまったのかもしれない。
* * *
王宮に辿りついたテイトの目の前には死体の山が積み重なっていた。
途中、ヒュウガと会ったが、2人の戦闘用奴隷を拘束している姿を見て【自由】という言葉を思い出す。
「ああ、アヤたんなら上の階にいるよ☆」
死体から目を背けたくて早足で階段を上っていくと、無理矢理こじ開けられた扉。
部屋は床から壁へ赤い液体が付着していた。
肉の部分がもう見えない、原型を留めていない人間だったモノ。
「アヤナミ様……」
「テイトか」
アヤナミは一枚も二枚も上手ということを、テイトは知っている。
よく、ミロクとも腹の探りあいをしてばかりだということも。
意味のない行動はしない、もしこのアントヴォルトに出向くことがあるならば。
(――それはミカエルの瞳に関係すること)
「パンドラの箱……が目的だったんですね」
「とはいえ、今の私にすればただの箱に過ぎないがな」
皮肉を込めて嘲笑った、つもりが、テイトは
「本当にそうでしょうか?」
と返し、アヤナミは紫の眼を細めた。
「何が言いたい」
殺気を込めて、テイトはびくともしない。
確かにテイトのベクライターとしての腕、そして戦闘能力は誰もが認める。
ミロクがバックについていることから、情が移ってしまう前は利用することも考えていた。
そっと、テイトは右手を、パンドラの箱に翳す。
「!」
そこに翡翠はなく、ただ緋色の染まったテイト。
忘れるはずのない、忌むべきミカエルの瞳そのものだった。
ザイフォンの発動が終わると同時に静かに蓋が開く。
(空だと……?)
「欲しいものは、ありませんでしたね……」
「空箱だと知っていたのか?」
「いいえ」
既に右手に浮き出ていた緋い魔石は消え、見慣れたテイトが、立っていた。
「貴様は何者だ」
嗚呼、悲しいと思えるじゃないか。
そう思える自分に嬉しかったのか、純粋に悲しかったのかは解らない。
一筋だけ頬を伝う液体を拭えば直ぐに仮面を被り直す。
「……オレは何処にも逃げませんよアヤナミ様。制圧後に事情聴取も拷問もお受けします」