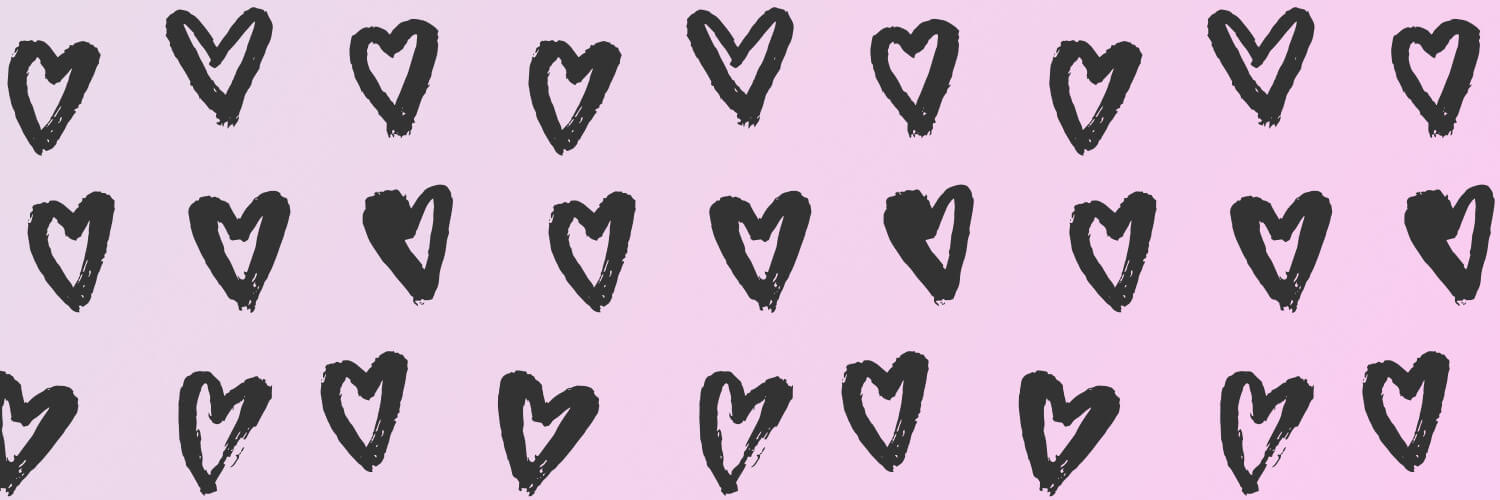今日は婚礼の日。オーブの問題が山積みでも少しぐらいの羽目を外しても文句はない。
宝石・ドレスと礼服で着飾る。
シャンパンを口に運び、貴族達は嬉しそうな笑みを浮かべた。
料理と内装は豪華だが、結婚式にしては人数が少ない。
花嫁が盛大な式典を嫌い、上級貴族で慎ましく行われることになった。
ホールの人々は主役の登場を今か今かと心待ちにしていた。
厚い壁の隔たりで室内の音は届かない。
人がそこにいるという雑音で(ずっとこのぐらいが良いのに……)と、少女はがっかりした。
暖かな日差しと小鳥のさえずりが聞こえ、心が落ち着く。
世話話やお世辞など聞きたくもない!
上質な布で特注の純白のドレス、果てしなくどこまでも長いヴェール。
式が質素でも、それは彼女が貴族の一員だと表している。
「お名前(女)、大丈夫?緊張しているみたいだけど……」
声を掛けられ、あと少しで入場だと気づく。
相手はこのオーブ首長国連邦の首相であるカガリ・ユラ・アスハの弟・キラ・ヤマトだ。
ファミリーネームが違うことを不思議に思って問うてみたら、コーディネイターだから生き別れになってしまっていたという。
オーブはコーディネイターを受け入れる数少ない国家だ。
この外で生きていくということは生命が最優先になる――すなわち、その身を偽ることが多い。
戦争が終結し、国の再建を手伝いたい。
自身の姿でオーブがコーディネイターも安全に暮らせる国なんだと示したい。
その希望から政治の世界に身を投じたと聞いた。
「いえ、大丈夫です」
見え透いた嘘をついたがキラは何も言ってこなかった。
この婚約が決まってからずっと考えている。
(本当に結婚していのだろうか?)と。
キラには愛を誓い合った女性がいると聞く。
コーディネイターの歌姫であるラクス・クラインだ。
著名人なので時折話題に出るが懐かしそうに語るキラを見ると心が張り裂けそうになる。
貴族に生を受けた以上、望まぬ結婚もあるかもしれないと腹を括っていた。
国を統べる首相の家に嫁ぐことになるとは予想はしないだろう。
この時代に政略結婚を推し進める母親を馬鹿らしく思う。
母が亡き父後1人で家の復興を目指し、権力望んでいることを知っている。
だが“相手が悪すぎる”。
再びキラが「いけるね?」と聞いたが、お名前(女)は返さなかった。
ホールの重たい扉が開くと大きな拍手が聞こえる。
緊張して鼓動が高まり、拍手と心音が頭に響いて耳障りだ。
本当に結婚していのだろうか――その答えは既に導かれているのに。
お名前(女)は司会からマイクを奪い取ると騒然とする。
サプライズイベントにしては花嫁の表情は硬く、苦しそうだった。
いつの間にか拍手は消え、ホールの視線が注がれる。
「私、お名前(女)・名字は――キラ様とは結婚いたしません」
「え!?」
「どういうこと??」
「なんで!?」
様々な反応が飛び交うがこの気持ちを話さない限り、結婚は白紙に戻らない。
キラも目を丸くして驚いているのが見えて申し訳なく思う。
自分の家と首相の家に泥を塗る行為でも、オーブの――自身の信念を曲げるわけにはいかない!
「キラ様には愛し合った女性がいらっしゃいます。それに私の母一人の勝手な都合で政略結婚などしていいのでしょうか?決して戦争は他国同士の問題ではありません!内戦も考えられます。それはカガリ様が言っておられた戦火の火種を生むではないのですか!?だからこそ私はこの結婚はできません」
先の大戦を思い出した貴婦人は涙を拭う。
女性は愛おしそうに子供を抱きしめる。
しんと静まった会場。
一人だけその言葉に納得できずお名前(女)をホールの外へ誘うのはキラだった。
「ちょ、ちょっと!あの!」
お名前(女)が酷く抵抗するのでキラは背中と膝の裏に手を回し――お姫様抱っこで無理矢理連れ出す。
その間も暴れるからドレスに皺が寄り、同じようにキラの眉間も皺が寄った。
キラがお名前(女)を下ろしたのは中庭だった。
「何するんですか!」
「君こそ、なんて馬鹿なことを言うんだ!」
「あなたこそ、そんなことを人に向かっていうものじゃありません!ラクス様がいらっしゃることは知っていますし、ラクス様もこんな結婚は望んでな――?!」
ぐいっと引き寄せられて唇が重なる。
キラを押し返そうと必死に力を込めるが全く効果はなく、されるがままキスするしかなかった。
唇を離すとキラの唇に赤いルージュが移っていて(嗚呼、キスしたんだ)と再認識させた。
お名前(女)から手を握ったこともないし、キスなんて求めることも求められることもなかった。
結婚するのにそれもどうかと思ったが、それは今は置いておく。
「ラクスは君と僕が結婚することも全て知ってる」
「え?」
「それに僕はラクスのことは好きじゃないんだ……お名前(女)が好きなんだ。初めて会った時から好意は持ってたし、それが政略結婚だったとしても君が僕の物になるならそれでいいと思った。お名前(女)は僕のことが嫌い?」
「それは、その……好きです」
「なら何も問題ないじゃないか」
ほっとしたように微笑むキラをみて、心臓がバクンと跳ねる。
ホールに取り残された来賓客になんと言うか気が重いが、繋いだ手は居心地は心地よかった。