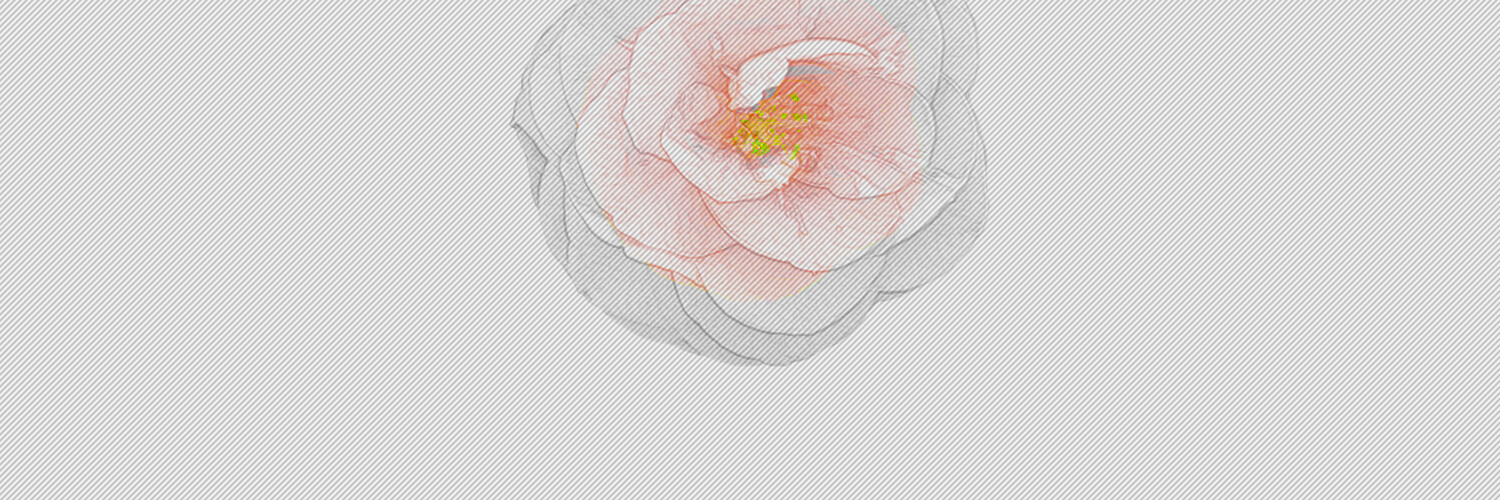海馬は今日もノートパソコンと睨み合っていた。ここ数日、部下の大きな失敗もなければ、今まで止まっていた企画も動き出し、作業も順調に進んでいる。これなら明日はオフにして遊戯と出かけることもできる――そのぐらい絶好調だった。何故こんなに作業が捗っている理由は解っている……遊戯が帰ってきたからだ。睡眠も大事な休息だが、モクバと過ごす時間と同じぐらい、遊戯と過ごす時間は癒される。
不意に鳴った電話の呼び出し音に海馬はイラッとしたが、慣れた手つきで受話器を取る。
「なんだ」
「社長、武藤遊戯様がいらっしゃっております。どうなさいますか」
「わかった、通せ」
正直、意外だった。帰国して自宅に顔を出していないことは知っていたし、遊戯から自宅に泊まる連絡は受け取っていた。海馬の家と違い、遊戯の家は暖かい。水入らずでゆっくりしてると思っていた。
ドアを何度かノックされて「入れ」と言うと、ひょこっと遊戯の顔が見えた。
「海馬くん、おはよう」
「ああ、おはよう」
挨拶はどこか淡泊で……ソファーには座らず、真っ直ぐこっちへやってくる。デスクを挟みに対面する形で遊戯は言った
「ねぇ、海馬くん。ボクとデュエルしようよ」と。
「突然どうした」
目は充血して目元の腫れも収まっておらず、散々泣いた後だとわかった。虚ろで、冷めた瞳。どんな理由であれ、自分以外の存在で遊戯が泣くなどあってはならない。問いに応えることはなく、遊戯はソファーに座った。
「遊戯、何があった」
「仕事が終わるまで待つよ。その間、デッキ調節してるから」
持っていた紙袋から取り出したのはブースターパックの山で、慣れた手つきで開いてゆく。
「遊戯ィ!貴様、オレを怒らせたいのか!?」
デスクを叩き、海馬立ち上がる。遊戯は手を止めても、動じなかった。
「イライラさせてごめんね。夢にもう一人のボクが出てきたんだ……今はそれか言いたくない。本当にごめんなさい」
「チッ」
怒りで震える手を抑え、椅子に座り直す。ここまで怒りがこみ上げてきたのは久々で、怒鳴るつもりなどなかった。
遊戯と<遊戯>は運命共同体とでもいうのか……“相棒”“もう一人のボク”この呼び名だけで互いがどういう存在か伺える。傍から見るとこんな状況は長く続かないことはわかりきっているのに、二人は生涯共に生きることを望んでいた。<遊戯>が全ての記憶を取り戻すまでは。
海馬もそれはよくわかっていて、<遊戯>と決別できていない今、遊戯はナーバスだし、夢の出来事とはいえ乱されるのは自然だろう。どこぞの輩に泣かせられたのかと思ったが……海馬はため息をついた。
海馬は脳内で時間を逆算して予定を詰めてゆく。夜以降の予定を配慮すると今から2倍、いや3倍のスピードで片付けないと難しい。小休憩する時間もなさそうだ。海馬にとってこの展開は都合が良く、遊戯を完全に自分のものとするのにまた一歩近づいたわけだ!
「遊戯、良いことを教えてやろう。明日は休めそうだ」
「ふ~――ん?えっ!?本当?!…………。ちょっと、海馬くん、ずるいよ!」
「フフフ……ワハハハハハ!!冷めた表情もソソられるが、今はオレに乱され、他は眼中にないといったところか。クク……愛しているぞ、遊戯」
海馬は何事もなかったように書類に目を通し始めた。
遊戯と海馬は向かい合うように海馬コーポレーションの屋上にいた。海を望むヘリポートはほぼ無風でデュエルするにはベストな状況だ。沈む夕日が童実野町を照らす。
「無理言ってごめんね。お仕事、本当に大丈夫?」
「ああ」
お互いのデッキをシャッフルする。
あの後、海馬は鬼のような勢いで仕事を片付けた。部下もその勢いについてこれるかというと別問題で、段取り悪く書類を待たされた間にデッキ調節したり無駄な時間は一切なかった。
仕事中心の海馬でも、招待されたデュエル大会はエキシビションで出演していた。宣伝目的だから最初から期待はしていないが、自分が満足できるデュエルはできなかった。その度<遊戯>とのデュエルを思い出し、決闘王に勝った遊戯の強さに思いを馳せた。
闘いの義の前――デュエルから遠ざかる前、遊戯とデュエルしたことがある。勝つのは決まって海馬だった。“慣れ合い”“デュエルごっこ”とも言えるそれは、デュエルに全身全霊を賭ける海馬にとって吐き気がするほど嫌いだったが、遊戯と時間を共有するには一番適していたし、純粋にゲームを楽しむ遊戯の笑顔を見ると自分が忘れていた楽しみ方を思い出した。それでも遊戯と全身全霊で闘いたい気持ちは常にあった。
遊戯は
「ボクが先行でいい?」
そう言いながらシャッフルした海馬のデッキを差し出した。
「構わん。遊戯、本気でこい!」
「えー、自信ないなぁ……」
デッキをデュエルディスクにはめると自動的にライフポイント表示される。
「「決闘デュエル!」」
「ボクのターン、ドロー!」
柔らな顔は決闘者デュエリストらしい表情になる。
「ボクはモンスターを場に伏せ、2枚リバースカードをセット!ターンエンド!」
時間を取らず、遊戯のターンは終了した。
遊戯の表情はわかりやすい。元々ポーカーフェイスが得意ではないし、真剣なデュエルになればなるほど読みやすい。海馬は直ぐ手札がよくないとわかった。
「オレのターン!ドロー!」
海馬はこの賭けの真意を掴めずにいた。このデュエルをする理由は夢としても、急に振ってきたこの賭け自体の理由は考えても答えはわからず、遊戯に問うても答えなかった。いくら真剣な表情でもデュエルに持ち込んだ時点で賭けの勝負はついている。
教えられた条件も勝ち負けについて指定しなかったし、最初からこのデュエルを本気でするつもりはなかった。そう、単純に自分にデュエルする気にさせて欲しかったのだ!海馬の本気で闘いたいという願望は打ち砕かれるし、未来のロードを賭けておきながら本気にならないのは海馬の美学に反する。
バトルシティの決勝戦・天空決闘決闘場で海馬は<遊戯>が過去に囚われた愚か者に見えた。今対峙する遊戯も、アテム……“もう一人の遊戯”という過去に囚われ、<遊戯>以上の愚か者とさえ思う。遊戯はそれを理解しているから、問題がややこしくなる。
海馬は思う。
(遊戯……僅かでも未来へ進む気があるならば、オレがお前の心に存在する<遊戯>に引導を渡してくれる!!)
この賭けでするデュエルは――遊戯の人生を賭けたものだ!
海馬は今しがたドローしたカードを手札に加え、じっくり見つめる。
「その気にならないか……。ならば今、オレがさせてやる!オレと――お前の未来へのロードを賭けて! オレは手札から魔法カード《ドラゴン・目覚めの旋律》を発動。手札からカードを1枚墓地へと送り、デッキから攻撃力3000以上守備力2500以下のドラゴン族モンスターを2体手札に加える」
慣れた手つきでカードを墓地へ送り、デッキから2枚引き抜く。
遊戯は
(まさか!)
と思ったが、心臓の動悸が収まらないまま海馬の手元を見守る。
魔法カードの内容を聞けば海馬が何をしようとしているか手に取るようにわかる。この条件に当てはまるモンスターは青眼の白龍ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンしかいない!
召喚するには2体生け贄を捧げなければならず、海馬の場にはモンスターはいない。ということは、たった1ターン目でそこまでのカードを引いたことになる。
「手札から魔法カード《古のルール》発動!オレのプライド、そしてオレの魂――出でよ!《青眼の白龍ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン》!」
遊戯がわざわざ裏側守備表示でモンスターを出したということは、リバースした時に何らかの効果があるのだろう。《青眼の白龍》を召喚した今、海馬に攻撃宣言しない選択肢はなかった。
「青眼ブルーアイズ、裏側守備表示モンスターを攻撃しろ!滅びの爆裂疾風弾バーストストリーム!!」
青眼の白龍の攻撃を防ぐモンスターはレアだ。遊戯のモンスターも攻撃と共に消え去り、一瞬だけモンスターの姿がソリッドビジョンに映った。
「《メタモルポット》のモンスター効果発動、互いに手札を全て捨て、5枚ドローする」
「クッ!」
海馬は顔をしかめながら、カードを墓地に送る。魔法カードでデッキからサーチした《青眼の白龍》を墓地へ送るのは悔しい。が、デッキには墓地から場と手札に戻す方法カードはいくらでもある。
「オレは場に2枚カードを伏せ、ターンエンド」
遊戯は映しだされた青眼に見入る。今までこの位置から光景を――海馬と青眼の白龍を何度も見てきた。対峙していたのは遊戯ではなくもう一人の遊戯で、海馬はいつも<遊戯>を見据えていた。好戦的で威圧混じりの視線は今は遊戯に向けられている。どこか穏やかなのは、きっと遊戯だからだ。涙が今にも零れ落ちそうな瞳で遊戯も真っ直ぐ海馬を見つめた。
「海馬くん……ありがとう。大好きだよ。これからはもっとデュエルしよう。もっと!――ボクのターン、ドロー!」
「サイレント・ソードマンで、プレイヤーへダイレクトアタック!」
「クッ!」
海馬のライフポイントが0となり、ソリッドビジョンの映像が消える。<遊戯>を倒した実力は本物だ。カードの引き、戦略共々素晴らしい。海馬は心から悔しかった。その感情を顔に滲まると遊戯はバツの悪そうな顔をしていた。
「どうした」
「ううん……」
遊戯の言いたいことはわかる。<遊戯>と違い、勝ち負けに拘らないからこそ海馬の歪む顔が酷く見えるのだ。しかしこればかりはどうしようもない。この気持ちがあるから見果てぬ先まで続くロードを進むことができる。遊戯を――追いかけることができる。
「そんな顔をするな。お前はオレが“世界で唯一認めた好敵手ライバル”だ」
「海馬くん」
夕日は完全に沈み、空は紺色に染まっていた。
海馬は携帯電話をかけたかと思ったら「磯野、15分後に下に車を回せ」と一言で切ってしまう。
「ねぇ海馬くん、ちょっと遅いけど今日――モクバくんと夕飯食べれるかな?」
「そうだな。連絡しておくか」
海馬邸、モクバ……次々電話をかける海馬は慣れたもので、遊戯はそんな姿を横目に月をぼんやり見上げる。夜になって気温も下がり、風が吹き付けると寒さを感じた。小さなくしゃみでも海馬は見ていたようで、腕で引き寄せられて遊戯と海馬の身体がくっつく。遊戯も腰に腕を回すとより密着し、海馬の体温を感じた。
「ああ、そうだ……8時半には戻る」
頭の上で交わされていた会話が止まり、連絡が全て終わったのだとわかった。
まず社長室に荷物を取りにいかないといけない。遅れるとモクバと過ごす時間も遅れてしまう。遊戯は名残惜しそうに海馬から離れると屋上と室内を繋ぐエレベーターに歩き始める。
「遊戯」
「どうしたの?早く戻らないと……」
「デュエルはお前の勝ちだ。だが、賭けはオレの勝ちだ。約束は果たしてもらうぞ」
「ああ……そうだね」
遊戯は言われるまで賭けのことはすっかり忘れていた。海馬は自分が優位になれることは絶対に忘れない。早く海馬邸に行きたいこの状況で無茶ぶりをされても正直困る。「後で聞く」と提案しようと思った矢先――
「遊戯、お前の全てをオレに捧げろ。心……身体、未来……人生の全てだ。そして誓え!オレと共に生き、そして死ぬと」
胸がカッと熱くなるのを感じた。真剣な表情で言うものだから
「君、その言葉の意味わかってるの?!」
遊戯は強い口調で返答してしまう。
「無論だ。お前に拒否権はないがな」
勘違いでなければこれはプロポーズだ。お互い唯一無二の存在であることに違いないが、こんなこと言われるとは思ってもみない。遊戯は照れながら伏せ目になるが、気にも留めず海馬はコートをなびかせながら早々歩いて行ってしまう。
「遊戯――この海馬瀬人の伴侶となれること、誇りに思え」
不敵な笑みだ。遊戯はこの表情に弱く何も言い返せなくなるし、心拍数が上がる。心を落ち着けるように深呼吸をして、海馬の背中を追った。